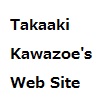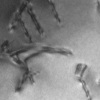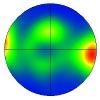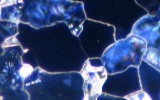1) 独自性のある手法:
コピー-改善方式 |
|
| ①師匠 |
独自性のある手法で研究している研究者(以下、師匠)の所に行く。 |
| ②完全コピー |
独自性のある手法を完全コピーする。
・師匠から研究手法を習う。
・完全コピーが出来たかを評価する。
・完全コピー出来なければ、師匠と議論する。
・議論に基づいて、完全コピーを試みる。
・完全コピー中に改善の余地がないかを考える。
・完全コピー中に師匠と改善の余地がないかを議論する。
・完全コピーが出来た後も改善の余地を探る。 |
| ③改善 |
独自性のある手法を改善する。
・改善方法を思い付いた場合は、改善に取り組む。
・改善に取り組んだ結果を評価する。
・改善していれば独自性のある手法になる。めでたい!
・改善していなければ、完全コピーに戻る。 |
| ④さらに改善 |
改善した手法をさらに改善する。
・さらに独自性が高まる。めでたい! |
| ⑤発表 |
|
| 2) 独自に考えたテーマ |
|
| ①目的 |
研究プロジェクト立案能力があることを示す。 |
| ②必要性 |
助教・講師・准教授・教授になったときに学生さんの研究テーマを考える必要が出てくるから。
それを考えれる(と思われている)人が取られている気がする。
【参考図書】
・理系のための研究生活ガイド第2版(研究テーマを決める14の原則、58-80ページ、坪田一男)
・やるべきことが見えてくる研究者の仕事術(「好き」よりも「得意」にこだわる仕事術、27-42ページ、島岡要) |
|
自分で雇用を確保している場合。
学術振興会特別研究員
フンボルト博士研究員
上司に理解がある場合。
上司が独自に考えたテーマを面白いと思ってくれた場合。 |
| 3) ブラッグの戒律 |
【参考図書・ウェブサイト】
・宇宙化学・地球化学に魅せられて(小沼直樹、178-181ページ)
・香内晃氏による低温研ニュースNo.23の巻頭言。 |
| 4) 試験的実験 |
|
| 5) 自分ブランドの構築 |
|
|
【参考図書】
・パーソナル・マーケティング(本田直之) |
|
【僕が考えてきたこと】
大学院生:
・超高温高圧下での元素分配
・超硬合金アンビルで高温下36 GPa 発生
博士研究員:
・高温高圧レオロジー、地球の熱的化学的進化、マントル遷移層領域の変形実験 |
| ①重要性 |
自分の強み・オリジナリティに基づいて、他の研究者との差別化を図り競合優位・市場価値を高める。
どこかに採用して欲しいと思うなら、こんなに役に立ちますよと発信した方が良い。
なぜあなたを採用する必要があるの?という問いに答えられるようにしておく。 |
| ②研究分野の絞り込み |
【自分の場合】
地球惑星科学・地学(研究対象=地球・惑星)、
→地球深部科学(研究対象=地球・惑星の深部)、
→地球深部物質科学(研究対象=地球深部の物質)、
→超高圧実験岩石学(研究対象=地球深部物質×研究手法=超高圧実験)、
→超高圧実験レオロジー研究(研究対象=地球深部物質のレオロジー×研究手法=超高圧実験)
→超高圧変形実験レオロジー研究(研究対象=地球深部物質のレオロジー×研究手法=超高圧変形実験)
→ここまで来ると独自性があると思う。
申請書にそう書いていて怒られたことはまだない。落ちたことはあるけど…、関連性は不明。
【参考図書】
・やるべきことが見えてくる研究者の仕事術(島岡要、20-22, 59-72ページ)
・理系のための研究生活ガイド第2版(坪田一男、64-66ページ) |
| ③方法 |
・重要性の明確化
・独自性の明確化
・情報公開(学術雑誌の出版、学会発表、ウェブサイト公開) |
| ④評価 |
・学術論文の査読依頼が来る?
・招待講演を依頼される? |
| 6) 参考図書 |
・院生・ポスドクのための研究人生サバイバルガイド(菊地俊郎)
(どうすれば独創的なアイデアが生み出せるか、75-77ページ、気づく力の大切さ、77-79ページ) |