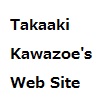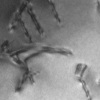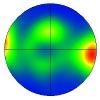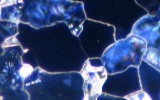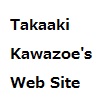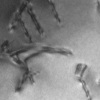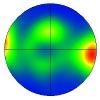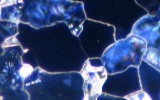|
コミュニケーションの手助け(話のネタ)になる。
相手の理解度が分かる。それに応じて対策が出来る。
相手にとって締切が出来るので、作業に取り掛かるようになる。
(締切がないと作業に取り掛からない人が多い。)
早く理解が進む。 |
| 1) 論文読解 |
|
| ①主要参考論文読解 |
論文読解方法を説明する。
要約を作成する宿題を出す。
読み終わった所から解説する。
2014年春セメスターは、Kohlstedt et al. (1996 PCM)。 |
| ②速読・斜め読み |
|
| 方針 |
研究内容の全体像を捉えてから、段階的に詳しく読む。 |
| 順序 |
題名 (読むに値する学術論文かどうかを判断する)
→著者(著者の過去の学術論文を読んだことが有る場合には主張・手法に見当を付ける)
→要旨(短い文章の中に重要性、手法、結果、議論が書かれているので、読んで大枠を捉える)
→図 (図は読者に伝えるべき情報を分かりやすく要約している(はずである))
→議論(議論の内容は重要である)
【参考図書】
・科学者として生き残る方法(F. ロージ・T. ジョンストン)
(論文・レターの構造:タイトル、要旨、序論、結論、参考文献、178-179ページ) |
| 2) 予習 |
テキストに書いてあることを調べて理解すること。 |
| クイック&ダーティー |
宿題は完成度50 % くらいでもってくるように指示する。
改善の仕方(完成度の高め方)を教えるのが仕事。 |